同じ目線でディスカッションできる存在として、経営パートナーや経営チームとの出会いは大切だと思います

株式会社プロジェクトカンパニー
事業内容と今後の展開について教えてください。
主に日系大手企業様向けのデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進支援を行っております。DX戦略立案から新規事業開発・既存事業変革支援、そしてデジタルマーケティングやUI/UXの改善まで一連のDX支援サービスを一気通貫で提供できることが強みです。
短期的にはDXの領域でシェアを高め、純粋想起されるよう事業拡大をしていきたいと思っていますが、弊社ミッションである、成果にこだわり、成果のためにプロフェッショナル人材が集まる「プロジェクト型社会の創出」を実現するためにはまだまだスタートラインに立ったばかりです。弊社は2045年に売上高1兆円となることを目指しており、そのために短期的にはデータ分析やシステム開発など現在のDXコンサルティング事業のラインナップ拡大に資するサービス、中長期的にはDXが進んでいない業界・業態に切り込んでいけるサービスの開発やM&Aも検討しながら、事業を拡大していきたいと考えています。

起業のきっかけ・これまでのキャリアについて教えていただけないでしょうか。
東大の学友含め「受験」と「就活」という入り口のところでは頑張るものの、その中で成果を出すことにフォーカスできていない人が多いと感じていました。優秀なはずの彼ら/彼女らの目は輝いておらず、このままでは日本はダメになるという危機感を抱いたことが起業を志したきっかけです。
大学卒業後は、コンサルティングファームで企業変革の経験を積んできました。コンサルティングファーム在籍時にデジタル技術は日進月歩で進化しているにも関わらず、企業の取り組みはウェブサイト制作やID管理などデジタルに関する表層的なものが中心でした。表面的な小手先のデジタル化ではなく、会社内部の考え方やビジネス・組織自体をデジタルベースで考える行動変容が必要であると常々感じていて、お客様とのディスカッションの中でその方向性が間違っていないことが確信に変わっていきました。そのため、日本企業にとっての最重要課題は今で言うところの「DX」であると考え、このフィールドで起業しました。

土井社長の生い立ちについて教えていただけないでしょうか。
父は囲碁棋士、母は音楽家という実力社会に生きる両親の背中を見て育ち、自分自身、幼少期より音楽やスポーツに打ち込み勝負の世界に生きてきました。小学生のときはピアノコンクールで入賞し、高校・大学のときはハンドボールに打ち込み、それぞれ相応の成果を上げてきたと自負しています。
ピアニストを目指していた頃は世界でNo.1になるという目標を持っていましたが、その夢が断たれた時に、それならばより大きな夢を追いかけないと面白くないな、と思いました。自分の可能性を広げるためには、優秀な方が集まる環境に身を置くことが良いと考え、東京大学への進学を目指すことに決めました。
大学入学後も進路については悩みました。理系だったので研究者を目指す道もありましたが、研究者は一つの研究が評価されるまでに何十年もかかる世界です。結果やフィードバックが明瞭かつ短期間で分かる分野でPDCAを必死に繰り返すことができ、グローバルで勝負できるという私の性格・強みを鑑みると、ビジネスの世界により適性があり、そこでNo.1になりたいと考えるようになりました。
SBIからの出資経緯について教えていただけないでしょうか。
ある新年会で北尾さんとお話しさせていただく機会を頂戴し、弊社がSBIグループ各社のDX推進や新規事業開発のご支援をさせていただいていることや、今後の成長目標についてアピールをさせていただいたことがきっかけで、出資をご検討いただくことになりました。その会には錚々たる経営者の方々がご参加されていましたが、やはりその中でも北尾さんのオーラは圧倒的で、これまでの経験の中でもひときわ緊張を感じたことを今でもはっきりと覚えています。
出資以前にSBIグループをご支援させていただくことになったきっかけは、SBIグループのある会社の社内制度づくりをされていた方から案件をサポートするお仕事をいただいたことです。ある日のミーティングの場で、たまたま別のプロジェクトの話題になり「私ならお手伝いできます。やらせてください。」と手を挙げてそのプロジェクトを任せていただき、結果として大きな成果を収めることができました。その後もグループ各社で様々なプロジェクトを任せていただくようになり現在に至ります。

SBIの評価・良い点・出資受け入れの決め手は何でしょうか。
北尾さん、川島さん、髙村さんをはじめ、SBIグループ各社の経験豊富な経営者の方々からアドバイスをいただき、経営者としての視座を引き上げていただいたことはありがたかったです。出資以前からグループ各社をご支援させていただく中で、会社として肌感覚や雰囲気が合いそうだと感じていたことも大きな要因でした。
また、SBIは経営層と現場が投資先のビジネス拡大に対して強い当事者意識を持っていると感じました。担当キャピタリストの田中さんより出資前から「SBIグループがどんな支援をできるか」というお話を常々いただいており、実際に地銀さんやパートナー企業さんを数多くご紹介いただき、今でもご紹介先のご支援を継続させていただいています。いずれのケースについても、ご紹介いただけなければ結びつかなかったようなご縁であり、弊社の顧客基盤拡充のご支援をいただけたことに大変感謝しています。
結果として、創業来掲げていたマイルストンとしての「創業6期目での上場」を無事達成できたことも、SBIから出資いただけたことによる影響が大きかったと考えています。
起業後に直面した壁や困難があれば教えていただけないでしょうか。
壁や困難というほどではありませんが、1つの案件で深く入り込んで成果を出せば、同じ会社の他の案件も獲得できることは早い段階で検証できていましたが、同様のスタイルが他のクライアントにも通用するのかは不安でした。SBIグループの様々な案件を通じて、我々のスタイルが正しかったと検証できたことは助かりました。
組織が大きくなるにつれて私との距離が遠くなり、私が思い描くコンサルティングのスタイルや会社の方向性とズレが生じる社員が出てくることもありました。弊社の仕事スタイルや行動規範、すなわち企業文化を浸透させるべく入社研修時や毎週の朝会などで私が何度も徹底して伝えていくことで、組織全体が徐々に同じ方向を向くことができるようになりました。組織が大きくなる過程では企業文化を明確に伝えることが特に大事だと感じました。
「企業文化に合わない人だろうと、採用しなければ会社が回らない」という意見もありますが、組織に合わない人をそのままにしておくと会社として合わせるべき焦点や向かうべき姿がぼやけ、そこからの事業拡大が難しくなります。また、企業のカラーが薄れて、魅力的な候補者の採用もしづらくなるという悪循環に陥ってしまいます。企業文化に合った人を採用すること、企業文化を浸透させることは非常に大事です。

経営者として日々大切にされていることを教えてください。
ラストマンシップです。どんな些細な事象でも全てはトップである自分の責任であるということは常々意識しています。弊社が採用する方に対しては全員の人生を背負う覚悟で採用していますし、社員がミスしたときでも、他の方から見れば「さすがにそれは土井さんの責任ではないのでは?」ということであっても最終的には全て自分の責任だと思っています。
若手の起業家や今後起業をされる方に向けてアドバイスをいただけないでしょうか。
会社にとってはビジョンが最も大切です。自身が描きうる最も大きなビジョンを掲げるのが成功のキモであり、中途半端なものだと一定規模で達成してしまい会社の成長が鈍化するでしょう。 私は停滞する日本の将来に危機感を抱いたことがきっかけで、成果にこだわり、成果のためにプロフェッショナル人材が集まる「プロジェクト型社会の創出」というビジョンを掲げ弊社を共同創業しました。そのビジョンに対して誠実に、必死に向き合ってきたからこそ、お客様にも、社員にも、弊社を選んでいただけているのだと思っています。ビジョンを作るのは決して簡単なことではありませんが、私の場合は何に燃えるのか、どんな時に熱くなるのかを言語化するプロセスを経て、少しずつ作ることができました。
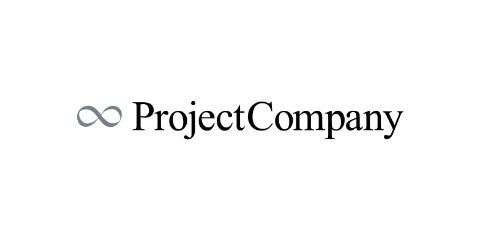
- 会社名
- 設立年月
-
2016年 1月
- 事業内容
-
DX(デジタルトランスフォーメーション)コンサルティング事業